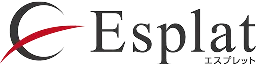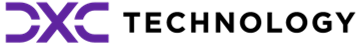日次リグレッションテスト自動化
株式会社SBI証券 様
“ワンチーム体制”で日次リリースを支える 品質基盤を構築 Esplat導入で属人性の解消と安心感を実現
業種
証券業(金融商品取引業)
従業員数
997名(2025年3月末時点)
導入範囲
顧客向けウェブサイト